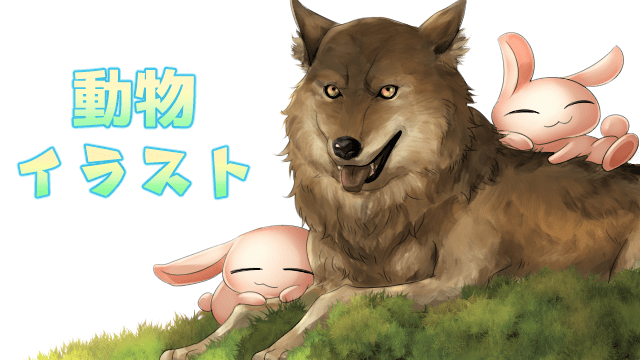絵を始めたばかりの方がよく悩むものといえば、目・髪などの顔イラストです。横顔や女の子など様々なパターンの顔の描き方を解説します。上達の近道を知り、お役立ち書籍・アプリ等とともに勉強しましょう。
この記事の目次
どんな絵を描きたいか考えよう
絵の表現方法は様々にあり、描く道具や手法の組み合わせによって、絵の画風・テイストが違ってきます。あなたが描きたいと思った方法を選んで、自分に合った絵のスタイルを決めていきましょう。
まずは、絵の種類、絵の描き方における基本の流れを紹介します。
絵の種類

大きくは『デジタル』と『アナログ』の2つに分類されます。
『デジタル』は主にパソコンを使った絵で、イラストソフトを使ってタブレットやタッチペン等、イラストを描くためのツールを使い、パソコンのモニター上に絵を描きます。
『アナログ』は、紙のキャンパス上に鉛筆や絵の具などの画材を使って描きます。画材の種類は、鉛筆以外にも、色鉛筆やコピックというマーカー、絵の具には水彩・油彩・水墨画まで様々な手法があります。
デジタル・アナログの分類以外に、線画がしっかりしたリアルな絵や、アメコミ風のイラスト、海外のアニメでよく使われる配色が豊かでポップなイメージのデフォルメテイストの絵等、様々なテイストの作風が存在します。絵をどこまでデフォルメするか、線の有無や色の塗り方・描き方の数だけ種類があるといえるでしょう。
上達するためには知識が必要
どんな絵を描きたいか決まったら、練習を重ねていくことでスキルは上達します。正しい絵の描き方の知識を身につけてから練習する方が、より効果的に上達することができます。全ての絵に共通する、基本的な作成の流れを覚えておきましょう。
最初は、人や動物の対象の『大きさや長さ』を『線や図形』を使って表現します。全体のバランスイメージを決めるための骨組みで、これを『アタリ』といいます。
アタリで全体像ができたら、肉付けして各パーツを描き『ラフ』と呼ばれる下書きを作成します。これで絵のイメージはほぼできあがりです。
ラフ(下書き)が完成したら、いよいよ『線画』(清書)をペンで描いていきます。描き終わったら下書きは消しゴムで消します。最後に、全体の色、パーツの色を決めて、色を塗って仕上げたら完成です。
顔は輪郭から描き始めよう

いよいよ人を描いていきます。まずは『顔の輪郭』から描き始めましょう。
輪郭を描くと同時に、おでこやアゴの広さも一緒に決めておきましょう。その後、顔のパーツを目・口・鼻・髪の順で描いていきます。それぞれのパーツの描き方のコツを覚えて説明していきます。
目は位置とバランスを考えて

目は、先に描いた輪郭の中に十字線でアタリをつけて、おでこの頂点からアゴの先までの間の半分より少し上ぐらいが、ちょうどよい目の高さです。高すぎても低すぎても違和感が出ますので、バランスを見ながら描いてみてください。
目の描き方は、目は大きいと可愛さや若さ、小さいと落ち着いた大人イメージになります。目玉は、白目と黒目の部分のバランスを考えて描いてください。白目・黒目どちらが多すぎても少なすぎても上手くは見えません。
さまざまな感情を表現できるのが口

口の描き方は、目とアゴのちょうど真ん中の長さを鼻とすると、その下にアタリをつけて、唇の幅や高さを決めていきます。目尻から鼻を通り、反対側の唇の端を直線で結べるぐらいの位置が口の幅・大きさの目安になります。口の高さは、線や影を使って表現していきます。口の形は、漫画でキャラクター感を出すためにデフォルメすることもあり、描く内容によっては大きく形を崩すこともあります。
女性は厚みのあるふっくらした唇で、はっきり描いた方が女性らしい絵になります。男性は唇の幅を広めに取ってください。大きく口を開けた場合、アゴの位置が後ろに下がるので、横からのイラストを描く時は意識しておくといいでしょう。
意外と描くのが難しい髪

髪の描き方は、毛の流れが分かっていないと違和感が出てしまう難しいパーツです。まずは頭の形を把握できるよう、髪の毛のない坊主頭から描いていきます。
髪型のアタリをとって、全体のボリューム感・生え際・髪の毛の流れを決めていきます。生え際は、つむじを中心に放射状に流すように描いてください。髪は一本ずつではなく一束ずつ書かれていて、束が太いと髪の量が多いイメージ、細ければふんわりしたイメージになります。太い束と細い束をランダムにしてあげると自然な髪型になります。
毛先や頭の外側については、束をまばらにすることで適度なボリュームのある髪型を描くことができます。
体を描くコツを覚えよう

人の体の描き方は、骨格を理解して、体の動きを立体的に見る洞察力が欠かせません。
例えば、腕をバンザイすると肘はどこの位置に来るか?腕を曲げると手のひらはどの方向を向くか?これを理解しているかどうかでデッサンに大きな違いが出てきます。
体も顔と同様、まずは全体を描いてから細かいところを描いていきます。これから紹介するコツを抑えて、デッサンを繰り返し練習していきましょう。
アタリをとる

『アタリ』があるとデッサンもしやすく、早く上手になります。胴体を中心に、頭・腕・足のパーツにアタリをとっていきます。
アタリはあまり凝りすぎると、何度も描き直しをした際に時間がかかりすぎてしまいますので、あまり効率的ではありません。各パーツの長さを把握するのが目的なので、男女共通であまり難しく考えずシンプルなもので大丈夫です。
慣れてきたら線だけの針金人形でも十分です。形は大きく描くようにしてください。小さすぎると、長さや大きさがわかりにくくなってしまうので注意が必要です。
体の比率を考える

体の比率は、頭身からアタリを描いていきます。目安は、女性ならば身長140センチ前後なら6頭身、160センチ前後なら7頭身位です。男子は145センチ前後で6頭身、170センチで7頭身といったところです。
絵のテイストやキャラクターによって、3頭身~8頭身まで様々ですが、6等身~8等身のスマートな体形の場合は、等身の半分ぐらいの位置を股間にすることでスタイルのいい体形ができあがります。
脇から股間の半分ぐらいの位置が肘、股間から足の半分ぐらいの位置に膝があります。頭の比率が大きくなったら、手や足も比例して短くするようにして、バランスをとるとよいでしょう。
デッサン人形も役に立つ

『デッサン人形』は、人と同じ関節の動きをとることができる人形で、木製のほか、プラスチック製、3Dデジタル人形などがあります。
デッサンをする上でのサンプル資料として、アタリで描いた動作を実際に反映し、関節のつなぎ目を確認したり、立体的に人の動きを確認したりする時に役に立ちます。特に、難しいポーズを描く時は、デッサン人形を使うとよいでしょう。
アタリをとった針金人形に腕や足といったパーツ、関節の動きをつけていきます。この時、平面的にならないようデッサン人形等を参考にしながら、付け根を意識して立体的にイラストを描くようにしてください。
人物ではなく風景画が描きたいなら

思い出に残った場所、魅力的な風景は、いつまでも忘れないよう記録に残したくなります。描くならば上手く描いてみたい。風景画が描きたい方へ、描き方のポイントを紹介します。
実は、風景画は基本さえ抑えてしまえば簡単に描けるようになります。風景の描き方を覚えれば、人の絵とも組み合わせて使うことができるので、ぜひ練習してみましょう。
まずは身近な風景から

風景といえば、海や山、桜や紅葉、雪等を思い浮かべがちですが、あまりに美しすぎる景色は、絵で表現する良さが出ないことがあります。せっかくですから、自分しか描かない景色を選びましょう。
初心者は身近でよく見る風景の絵から描いてみることをおすすめします。家の窓から見える景色でも構いません。何度も練習することができますし、記憶に残っている風景なので、表現方法が上達していくのを実感しやすいからです。
頭でイメージすることも大事
風景の絵は構図が大事になってきますので、頭でイメージしながら描いてみましょう。初心者は下書きからおこすようにしてください。紙に鉛筆で薄く描いて、納得がいく構図になるまで、何度でも描き直しましょう。
構図が決まったら、下書きの時より少し強めに描いていきます。風景画は基本的に細かいところはあまり気にせず、雰囲気だけ描くだけで十分に伝わったりします。
奥行きも意識して

奥行きが描けるようになると、風景の絵に広さを表現することができます。また、人と一緒に描かれている時なら、人を引き立たせる効果もあります。
遠近法を使うと近くのものは大きく、遠くのものは縮小して小さく見せることができます。物の重なり合いがあるところは、奥にある物を部分的に隠れて見えなくすることで、奥行きを表現できます。
他にも、等間隔のフォルムを縮めて見せる短縮遠近法や、遠くにある物を薄くしていく空気遠近法といった奥行きの表現方法があります。
動物も描いてみよう

動物の絵の書き方は、種類によって体の仕組みや体格が違うので難易度は高めです。ここでは、人間との描き方の違いや種類別の特徴をお伝えしていきます。
今回は『脊椎動物』に絞って、人間と動物の構造の違いを学びます。最初に現れた脊椎動物は魚類です。そして、陸上でも生きることのできる進化した生き物が両生類です。
さらに、両生類が進化して爬虫類・鳥類・哺乳類が生まれていきます。様々な動物のイラストを描くことができるよう、それぞれの体の構造を覚えておくといいでしょう。
人間との違い

人間と動物の明確な違いは、人間は二足歩行で両生類・爬虫類・哺乳類の多くは四足歩行です。ここでは、四足歩行の動物と比較していきます。
まず、立体的に見た時に胴体の形が、頭の上から見ると人間は横に広く、動物は縦に長くなっています。また、人間の首は頭より細くなっていますが、動物の場合は頭よりも太いので注意しましょう。顔の表情は人間だけだと思われがちですが、実は動物も表情は豊かです。唇を薄く描いたり、眉の周りの筋肉の凹凸を描いたりすることで、喜怒哀楽を表現することができます。
目は白目が多いと人間っぽい表情を見せますので、動物の意思を伝えたい時は白目を増やすといいでしょう。他にも、骨格・体格・歩行の仕方・顔などのパーツの配置・毛の生え方に到るまで、人間とは大きく異なっています。
アタリはパーツ別に

動物の絵を描き始める時は、四足動物の場合は、胴体を肩周り・胸部・腰周りの3つのパーツに分割し、頭部・首・前足・後足・尻尾のつの結合パーツに分類します。関節の曲がり方は、例えば犬の場合、足は外側にはあまり曲がりません。そういった特徴を理解した上でアタリをとると、デッサンの時に変な感じにならなくなります。
鳥の場合は頭・体・羽の3つのパーツに分けてアタリをとっていきましょう。基本の形はどの動物でもこのどちらかになりますので、あとは動物の種類に合わせてパーツの比率を調整すれば絵は完成です。
肉食と草食で目線が違う

肉食動物の目は、正面から見た時は平面的に描くのに対し、草食動物の顔を正面から見ると、目が横についていて奥行きのある立体的な見え方になります。肉食動物は狩りをして食物を手に入れるため、距離感を正確に測れるよう2つの目が正面についており、草食動物は肉食動物に襲われる危機をいち早く察知できるよう、目が横についていると言われています。
例えば、馬は草食動物なので横に目がついているのですが、競走馬は目隠しのような物をつけています。これは、前に走ることに注意を向けさせるため視界を隠しているからです。
初心者に読んでほしい描き方がわかる本3選
初心者なのでもっと絵を上手くなるために、本でも勉強したい方へ、基本からまとめられている本を<3冊ご紹介します。
マンガの基礎デッサン 女のコキャラ編
初心者の方でもすぐ実践できる、女の子の絵の書き方に特化した本です。かわいいキャラを出していくための表現技法や工夫をこの本で学んではいかがでしょうか。
頭身の差や、プロモーションの違い、表情、メイクや髪型等、ちょっとした違いで魅力あるキャラクターができあがります。女の子に限らず、人のデッサンの基礎、デフォルメの仕方が紹介されていますので人の描き方の入門書としても役に立ちます。
スーパーマンガデッサン
人の絵の描き方をわかりやすく、デッサンの基本から解説されているので全くの初心者の方にもおすすめの一冊です。人間の動きの元になっている骨格や筋肉の仕組みまで掘り下げて紹介されています。
考えるデッサンを身につけ、上手く描けるようになるためのヒントやアイデアがいっぱい詰まっています。人の体を上手く描きたいという方は、プロの描き方が学べる内容になっていますのでぜひおすすめです。
やさしい人物画
短期間で人の絵の描き方を学ベるよう、ポイントを抑えて技法をまとめられている本です。初心者の方でも理解でき、芸術性の高い人のイラストが多数乗っていますので美術の教科書としても使える内容になっています。
この本に載っているノウハウを活かせば、人の描き方は怖いものはありません。美しい人の描き方を身につけましょう。
スマホやipadで絵が描けるおすすめアプリ

好きな時に、好きな場所で絵を描ける便利なアプリをご紹介します。最近は豊富な機能を持ったアプリが無料で使えることもあるので、ぜひダウンロードして気軽に使ってみましょう。
CLIP STUDIO PAINT EX for iPad

ipadでマンガ・イラスト制作、商用レベルのアニメ作画までできてしまうトップクラスの絵画アプリ。世界で300万人が利用し、多くの教育機関でも使われていて初心者の方が最初に導入するソフトとしてもおすすめです。
Apple Pencilに対応しており、タブレットながらまるで手書きのような感覚でイラストを描くことができますので、アナログ派の方にも安心してお使いいただけます。
お絵かき広場Spline

スマホアプリで本格的な絵が描けます。アプリと言っても侮ることなかれ、26種類のブラシと拡大も3000%までできるので、小さな画面でも細かい作り込みが可能です。投稿機能がついていてアプリのユーザー同士で共有して楽しむこともできますので、たくさんの人に絵を見てもらいたい方はこちらをお使いください。
メディバンペイント

パソコン・スマホ・タブレット、どんなデバイスにもクラウドで連携対応しているイラスト・マンガ制作ソフトです。
800種類のトーン・背景、50種類以上のブラシ、20種類以上の有名フォントが入っていて、初心者でもプロ並みの仕上がりの絵が描けます。
まとめ
人間・風景・動物を描くことは、絵を始めたばかりの初心者にとっては難しく感じることが多いと思いますが、こうしたコツを抑えておくことで、誰でも飛躍的に実力を上達させることも可能です。
知識は知っているのといないのとでは、表現する絵にそれは必ず現れます。勉強するのは時間がかかりますが諦めずに練習を繰り返し、魅力的な絵をたくさん描けるようになってください。